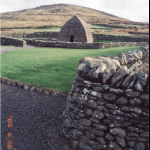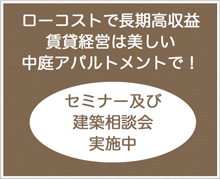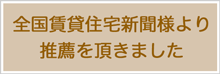素材
《感動の意味-「もと」になるもの-》
この稿を書きながら、目の前にある土壁にそっと手を触れる。うっすらと浅葱のさした土である。今、ここにいることを無条件で祝福してくれているような、しっとりとして、それでいて乾いた感触である。そう、あの時のなつかしい感覚でもある。
それは、設計という仕事を通して社会に出た3、4年目の頃であった。ある仕事を任された。施主、事務所、現場、多くの人が関わる中、多くの価値観が自分を問い詰める。過程のための過程と化した経済、いや「金」。何と無慈悲なことか。それでも当時、なんとか強がって何か「人間らしさ」と感ずる気持ちを持ち続けもしたが、同時にそれが、何とバカげてつまらぬものかとも思った。所詮、それは社会の荒波にもまれたこと、つまらない悩みと考えても、当時の自分にとっては余りある苦しみ辛さであった。朝起きても微熱が続き、喉がつかえ、自分の手を握っても自分の手という感覚が持てない。何とかしたい。何とかしなくては。ワラをもつかむ気持ちで、今まであまり読んだことのない分野の本を読み、夢中で建物を見て回った。いつしか、ある建物に出会っていた。戦禍の土で焼いたほんのり土色がかった灰色のレンガ積の教会である。手さぐりで建物中徘徊した。いつしか、そこに見ている自分でなく見せられている自分、感じている自分ではなく感じさせられている自分があった。自分の中にありながら、今までわからなかった自分以上のもの。自分でもどうしようも出来ない大きな喜びで、今自分が生かされていることを実感した。あきらめずに持っていた、いや、生まれる前から持っていたのかもしれない、頼りない細い糸が、はっきりと一本の太い線でピーンと全てつながったような、そんな感覚。感動? 言葉を超えた喜び。体の底から涙が溢ふれ宙に浮くようにも感じた。これなんだなあという実感と共に、教われたという感謝の気持ち……。
《素材の力》
また、このようなことを書くことをどうぞお許し願いたい。しかし、自分はそのような体験でしか、「その実感」を感じ、そして伝えることしか出来ないのである。どう思われようとご勘弁下さい。
このような実感、感動はなければないで、またあったとしても、それは多くの中の一要素としての問題でしかないと。……否! それは無視することが出来ない。いや、それを頼りに、それをよりどころに生きることが出来るもの。その存在の重さゆえに、ここで述べることになる。
そう、それは確かにその建物の「素材」のせいだけではなかったと思う。しかし、確実にその素材感が担っていたことも確かである。つまり、その素材感がなければ、私のその実感は無かったということである。現に、それ以後「素材感の持った」いくつかの建物に無条件で「同じ思い」を覚えることとなる。建物だけでなく、その建物を成す素材の力は思っている以上に大きい。
《芸術の意味》
建築に限らず、車、橋等工作物といわれる全てのものには、いくつかの機能が含まれているといわれる。「実用的機能」「物理的構造的機能」「情緒的機能」「地域文化的機能」等、そして、そこに前述からの「地球自然環境的機能」とでもいうべきものの考慮急務というのが、提言の別のかたちにもなっているのだが。ここでは、それと同時に「情緒的機能」の重要性について述べてみたいと思う。
いわゆる「雰囲気」。しかし、それは感性、感情を持った人間が物をつくる、そして受け取る上で、決して無視できぬものであろう。ただし、一般にそれが稀薄である場合や、それが第一の目的になりにくいことから、あっても判りにくい。もちろん、各々の機能は互いに絡まり合いながら働いている。そして、その「情緒的機能」は、時として第一義となることもある。それは、芸術の分野となろうが、感動体験はもちろん、前述よりその意味は思っている以上に大きいと思われる。
人は生きている。常にその死をその内にはらみながら。現代人の人間の棲む、生きるという深い意味を、また現代人の魂のやすらぎ、心の癒しを直接理解し共感し合えるのは、実はその「感性」「感動」「実感]、その情緒でしかないのではないか。いや、実はそのための他の機能ではなかろうか。前段でとり上げた「地球自然環境的機能」もしかり。「感動」「実感」の無いところから、生まれている全ての論理の何と暴力的なことか。それ程、重要なことのように思える。「人にどのような影響を与えるか」である。そして、それはまた、人を豊かな生活、倫理、芸術へと駆りたてる唯一の「もと」ではなかろうか。現代の限られた完結した人間系の中での芸術に、どこか「わがまま」を感ずるのとは対照的に。
《自然の素材》
かつて、パリの街の、白壁の美を追求した画家は、絵の具にその壁材そのものを混ぜ、壁を荒塗りするようにパレットナイフでキャンバスに塗り込め、描いたという。それでしか表現出来なかったのであろう。自分の内にあり、自分ではどうすることもできない実感、人が生きているという実感、生きていることを祝福、肯定される実感、喜び、感動のかえがたい担い手として「自然の素材」があろう。どんな感情、精神も物質、いやその素材を介してでしか伝えることが出来ないのではないのか。知を迂回することなく。手法、人工もそのためのものとなろう。
「自然の素材」。その存在の意味を、それを使うことの意味を、人は問うことができない。その存在は、人間よりもはるかに長く、人知を越えたものであろうから。もしかしたら、素材によっては逆に、人間の存在の意味をも知っていると言ってよいのかもしれない。
いずれにしろ、それでしか人間にとって人知を超えたもの、人間にとって必要な「自然」を実感し、伝えることができないのではないか。建築の素材が音楽における「音色」のように理解された時、建築の意味も素材の意味も生活の意味も、よりはっきりと、より生き生きと自覚できるのではないだろうか。

建物の「素材感」。フランス ・オーヴェルニュ地方
前略……なぜ、このようにかつての民家は、建築の過程がその都度都度美しいのか? 棟上げの木組みが美しく、木舞を掻き終えた壁の姿が美しく、塗ったばかりの泥の濡れ色が美しく、乾いていく泥壁の風情がいとおしく。たぶん、それは民家をつくっている建築の素材が、いわゆる建材ではないというところから来ているのではなかろうか。かつて、民家に使われた建築素材は、木であり、竹であり、革であり、泥であり、石であり、砂や砂利であり、稲藁であり、棕櫚縄であり、ほとんど現地で見い出される無償のものだ。無償であるとは、ほんらいなにもののためにあるのでもなく、そのもの白身としてあるものだということだ。樹は、柱や板になろうとして生えたわけではないし、砂利はコンクリートの骨材になるために存在するわけではない。建材というのは、セメントにあれ、プラスチックにあれ、合板にあれ、ガラスにあれ、アルミにあれ、メタルにあれ、あらかじめ建材としての意味を与えられ作り出されたものであって、無償の存在とはいえない。それら、そのあらかじめ与えられた意味以上でも以下でもない存在としてありつづけるだけだ。 そういう意味で、かつての民家を成り立たせてきた自然の素材は、柱になったり、壁になったり、屋根になって建材の一部になっているにしても、建材以上のものだ。いつでも、ほんらいの無償の存在に帰ろうとしているのだから。ゆるやかに時を刻みながら、木は腐蝕し、泥壁は水和し風化し粘土化していくのだ。
たぶん、建築に美しさやいとおしさを感じるとしたら、それはその建材の中に含まれている無償性によってであろう。その建築にどれだけの無償の存在が含まれているかによって、その分だけいとおしさや美しさを感じるのではなかろうか。無償性とは、いいかえれば自然との連続性ということであり、建築の無償性もまたしかりなのだ。
(「左官礼賛」小林澄夫著)

素材の無償性、浅葱土 ― 自然との連続性 ―
街の美しさ
《旅人の住む街》
かつて、人は自然の中で生き、土と共に生活していた。死の恐怖と一心同体であったが、生きていることそのものをいとおしいと強く感じていたことも確かであろう。そして、「まつり」があった。自然をふるさとに想い、常に「旅」をしている人間の、無条件の営みであったのであろう。
いつしか人間は、自分の生まれ育った自然を離れ、人間の社会だけで完結した便利な空間、「街」、いや「都市」をつくる。人が生きるために必要だと思う「もの」に「美しさ」というものを感ずるとしたら、その街の中でしか生きていない人々にとっては、自然の木も、面倒な枯れ葉の掃除のもとでしかなく邪魔となり、切り倒されていく。
旅人は旅をやめ、そこにはふるさとを失った「まつり」だけがむなしく残る。 まるで根無し草のように……。
《楽しい街》
街の本質とは何か? 集まって住むことの意味は? 街に住む、いや住まざるを得ない上で、決して避けて通れぬ問題である。ただ言えることは、自然を無視した人間だけの完結した街、いや社会は、それこそ便利で楽しいかもしれぬが、人間の、自然をふるさとに持つ旅人としてのストレスはどうなるのであろうか。自然とは別のサイクルの、人間系の閉じた社会、それは人間の営みの中でのみ生まれた目的のはっきりとした建材と同じで、「生きて」いく上では、そこそこ申し分はないが、いや今ではそのそこそこさえもままならぬ程と思われるが、「本当に生きているという実感」をそこに感ずることが、はたして出来るのであろうか。本当に「楽しい街」になり得るのだろうか?

石積みのロマネスク教会。フランスブルゴーニュ地方
《夢》
私は今、フランスの小さな村の教会の前に立っている。川の流れと戯れるように、うねうねと連なる畑の縁を、眼下に見下ろす、小高い丘の上に建っている小さなロマネスクの教会。大きな街のゴシック教会と違い、村々に必ず一つはあり、そして、それは今でも使われて、村の人々の心のよりどころとなっている。その土地の小さな石が、おそらく村人達自身の手によるのだろう、素朴に丹念に積み上げられている。そして、それをいちいち確かめるように、石灰と土とで包まれている。ちょうど追われた民が、失われた魂を悔い、そして残すかのように。無条件に美しい。どんどん世界はグローバル化し、ますます抽象化され、鉄とガラスの未来都市さながらの風景を呈す中、緑豊かな森や川の流れる、土壁や石の街並を想いうかべるのは、そんなに罪なことであろうか。せめて舗装された道でなく、士道の草花を愛でながら街を歩いてみたいのである。
重い扉を開け、教会の中に入る。底光りのするうす暗さに包まれる。ふっと日本の茶室と思った。いや、よくみると高窓から陽の差し込む土壁で囲まれた蔵の中にいるようにも感じた。いや、違う。だんだんと目が慣れてくる。うっすらと絵が描かれているようだ。そう最後にはっきりと写ったのは、明るく色鮮やかな、さわやかな縄文の森であった……。