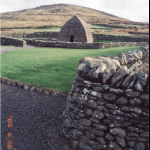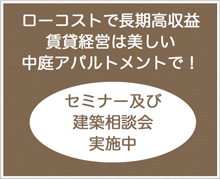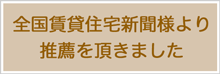アイルランドの自然
ゆるやかな丘の続く自然の地形なりの畑や牧草地の豊かな緑。そんな風景の中に点々と見えかくれする村々。教会の塔が愛らしい。フランスロマネスクの風景である。美しい。そうは思いながら、目本の自然を思う。豊かな木々、水面をたたえながら段々と広がる棚田。こんな以前にはあたり前の風景も今では少なくなったが、それにもまして本当に日本の緑は豊かであり、美しい。贅沢な感さえ覚える。フランスの田園風景のただ中にいながら、至極自分が東洋人であることを感ずる。
アイルランド。 ダブリンの町を出る。緑のじゅうたん。風が強いのと、天気がめまぐるしく変わるのを除けばフランスの田園風景と同じように思えた。しかし車で進めば進むほど、よく見ると木らしい木は生えておらず、はかなげに緑がはげている所は石灰岩の岩盤があらわれている。これは尋常ではない。
比較的肥沃な地に「タラの丘」はある。島国でありながら、その広さと開放感には圧倒される。アイルランド系アメリカ人、マーガレットミッチェルが小説「風と共に去りぬ」の最後のシーンで、主人公スカーレット・オハラに「タラヘ」と言わせしめたアイルランド人の心のふるさとであり、ケルトの聖地である。日本人の私でさえも、その丘の上に身を置けば、大地を感じ、その風景は心にきざみつけられる。




石垣“土をつくる”
アイルランドを西へと進む。高さ1メートル程の石垣が、道の両側といわず牧草地を縦横に延びる。牧草地、洋芝とクローバーである。時々ポツンとゴールが建ててあれば、そこがサッカー場となる。日本の公園の芝と違い、こちらでは芝は牧草であり、特別な存在ではなく雑草なのである。限られた肥沃な地域を除いて、畑はほとんど見あたらない。この石垣、島の西へ行く程間隔がせばまり、密度が高くなる。専らの土地の境界や牧畜の柵の役目もあるが、さらに白然のきびしい地域ではなんとわずかに“作った土”を飛ばされないための風よけの役目もはたす。
この辺の事情は1934年のドキュメンタリー映画の古典といわれているフラハティー監督の「MAN OF ARAN」に詳しい。アランとはアイルランド本島のさらに西、小さな島々の名称である。岩盤をハンマーで砕き、妻は本土から飛ばされて岩の裂け目や窪みにたまった土を手でかき集める。嵐の後、海岸に打ち上げられた海藻を家族総出で運び、これらと混ぜ合わせ“土をつくる”。ジャガイモを作る畑までいかなくとも、牧草が表面を覆う。こうした昔ながらの生活は、近代が進んだ現在でも一部で行われているそうである。アイルランドは文字通りケルト人の手で作った国なのだ。


紀元前600年頃から、ケルト民族は波状的にアイルランドに侵入してきた。ヨーロッパ大陸からの言語や文化を先住民に押しつけたと言われる中で、引き継いだ慣習もあった。優れた埋葬様式に関わる石の文化がその一つである。ケルトの人々は石の圧倒的な存在感と神聖さを直感的につかみとり、自らの文化の中に守り育てたといえよう。ヨーロッパ大陸のロマネスク時代の彫刻が建築と一体となっているのに対して、ケルトは先史の巨石モニュメントである野外の「立石」そのものに、決して静的ではない互いに中心をずらしながらの渦巻きやその他の図像、象徴を刻み込んだのである。風雨にさらされながらも大地に根をはったように立つ文様が施された立石の遺跡のいくつかを目の前にすると、その迫力とともに人知を越えた普遍的な神秘的な力を感ずる。
ここで忘れてならないのが石積造における労働の意味である。ローマ時代には奴隷の豊富な労働力を利用し、巨大な石材を自由に用いた。つなぎの石灰は用いる必要はない。中世の場合は奴隷による組織的な労働力はなく、建設現場のスケールは自然小さくなった。石は原則として人間が運べる程度のものである。当然それを石灰、漆喰でつながなければならない。石灰は重要な意味を持つ。ローマの石灰は極めて良質だが、中世の現地で石灰岩を焼成、沸化したそれは粗悪でもろい。言わばローマに比べ、ある意味では材料、構法の稚拙な中世の聖堂は、しかしながらその石の一つ一つを民衆の手で少なくとも自らの意志で積み上げて出来ているのである。しかも現代でいう実用的な意味のない、祈りの空間のためにである。石に対する畏敬の念にもまして、中世の石積造に無条件の美しさを感ずる。


ケルト修道院
世俗から離れ、禁欲と苦行により救いを得ようとする修道の道は、洋の東西を問わず宗教上の現象であろう。キリスト教の場合も4世紀エジプトに修道制の2つの祖型がみられるといわれる。完全な孤立的な行き方を取る隠修士(ハーミット)とよばれる修遺制と、各々個別的な生活を送るが、共同の修道日課に従って生活する集団的な生き方、共住制(シーノバイト)の2つであり、ともに広まっていくことになる。


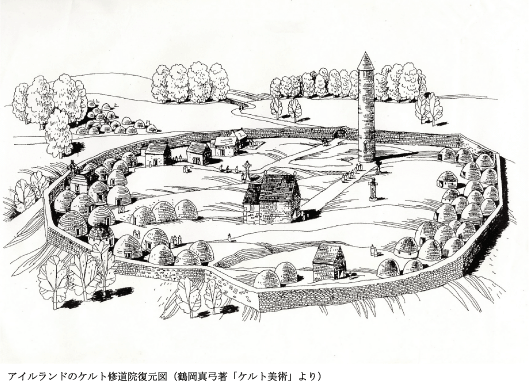
聖パトリックによってアイルランドにキリスト教がもたらされたのが432年、土着のケルト社会の自然信仰との融合を計りながらの布教により、ケルトの氏族社会は修道院を中心とする共同体へと変わっていった。たしかにそれはローマ教会のシステムとはずいぶん違っていたようである。まず教会よりも修道の場としての修道院が中心だったこと。ピラミッド型のローマ教会と違い、各教区を統括する首位司教がおらず、各々の修道院長を頭にあちこちで信仰による家族的集落をつくった。大きな建物の中に人がたくさん住んでいるのではなく、囲いの中に礼拝堂、食堂、学校、写本工房、それに蜂の巣状僧坊(ビーハイブハット)など、いずれも小さな建物がぽっぽつとあり、まわりには墓地が広がっている。
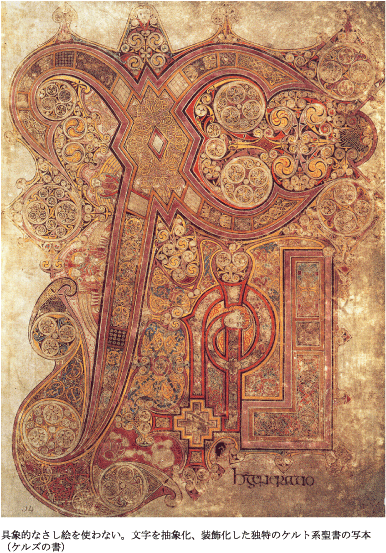
8世紀の「モリングの書」は聖モリング創設の修道院共同体の平面図をその最後の頁に付している。 そして、エジプトの砂漠の修道士とならび称された「エグザイル」精神-自らを故国から追放する精神-のケルト修道院士の禁欲主義的な修行は、その自然環境から触発されたのか、時としてなぜこんな所にと思われるような絶海の孤島に洞窟のような修道所を生み出すことにもなる。いずれにしてもそれらが大陸へとキリスト教の逆輸入の形となり、国外からも「聖人の島」と称されるようになる。具象的なさし絵を使わない文字等を抽象化、装飾化した独特のケルト系聖書の写本が生まれたのも、これら修道院からである。
素材
修道院の諸建物は、この地方の民家を見る限り、少なくとも屋根は木造が多かったであろうと思われる。それらは消え、今残っているものは全て石造である。石は主として石灰岩、砂岩、片岩、小石が混じったような人工的と思われる堆積岩風等であり、必要な所に花岡岩も使われている。
もう一つ重要な材料は、前述よりの石灰である。主に石積造の石と石の問の目地材となっている。風雨の強い地方の遺跡の外部には目地材を使用した形跡のほとんどないものもあるが、基本的には内外とも石灰の目地材で固めながら築いたと思われる。石灰岩の豊富な土地柄、おそらく生石灰をその場で沸化してそれに砂や土、砂利類を混ぜ使用したものと思われる。前述のようにローマの石灰はドロマイト系の良質のもので、フランスやアイルランドの石灰は粗悪なものが多く、もろい。各所の遺跡では色セメントで補修してある所も多かった。しかし、石灰と石との付着力の強さは想像以上と思われる。バイキングによって崩されたまるで大きな石のような石積造のかたまりを見ると、石と石灰との関係はどうしても何か表面的以上に計り知れない深いものがあるように思え、近代の強度追及の結果出来たセメントではどうしても換わることの出来ない部分があるのではと思えてならない。


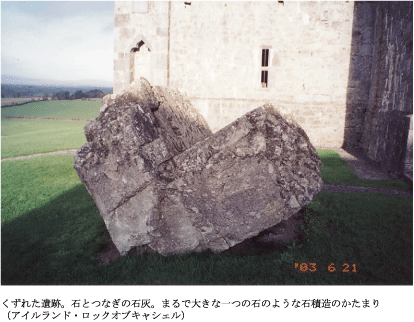

石灰をうす塗りし、仕上材として使用しているロマネスク教会の壁(フランス・トウールーズ)